山岳圏森林・環境共生学コース、地域協創特別コースで一緒に学びましょう!(コースの私的な紹介)
 山岳圏森林・環境共生学コースと、地域協創特別コース に興味をもってくれた人、ありがとうございます。
山岳圏森林・環境共生学コースと、地域協創特別コース に興味をもってくれた人、ありがとうございます。山岳圏森林・環境共生学コース、地域協創特別コースの「どういうところが面白いのか」を、私の研究分野(森林政策学・林業経済学)から少し紹介します。
1. 日本の7割がわかる
森林と中山間地域の農地を足した面積は、日本の陸地の71%。日本はほとんど「山岳圏」です。
温暖化対策、防災、天然資源、生物多様性、文化、どれも この7割を抜きには語れません!
2. 現代社会の問題点が集中的にあらわれている
もちろん問題も多いです(多いから研究しています)。
たとえば、農林地の過少利用の問題があります。世界的にみれば、森林は減少しています。一方で、日本では森林は利用が低調で「多くの人が手放したがる土地」になっています。全体としては不足しているのに、日本では余っている。どうしてこんな不思議なことがおこるのでしょうか?
また、過少利用にともなって、里山の生物多様性が損なわれたり、クマやシカ・イノシシなどが人間の居住空間に出没したり、様々な問題が生じています。
これらは、「農山村が不便なところだから生じている」といった単純なものではりません。現代の社会全体がもつ問題が、山岳圏で湧き出ているのです。だから、山岳圏で学ぶことは、社会全体のおかしなところを知るということでもあります。
3. 次の時代がつくられる瞬間を体感できる
同時に、山岳圏は新しい試行錯誤がたえず おこなわれている場所でもあります。
これからの日本(とくに地方社会)は、人口減少していくので低密度居住になっていくでしょう。そこで可能性が高まっているのが、地域の自然資源を利用しながら、環境負荷を低くしていくライフスタイル、そうした社会づくりです。自然資源を地域の財産とする、コモンズという形の実践も、山岳圏で取り組まれています。
これを学び、実際に自分でも関われる。とくに地域協創特別コースでは、そうしたプロジェクトに関わりながら(協創しながら)学ぶことになるでしょう。
4. 現場のただなかで学べる
信州大学農学部は、村にあります。山岳圏、あるいは地域協創の現場が身近にあります。社会の問題点と、その解決策は、現実のなかにあります。大学のなかでの学習は、現実を見るときの見方を養うものです。信州大学農学部は、この両方がセットにしやすい立地だといえるでしょう。長野県には、地域で面白い取り組みをしている人たちが大勢います。
もちろん、村にいるから自動的に現場に接することになるわけではありません。村にいても、地域とは何の関わりもなく学生時代を過ごすこともできてしまいます。重要なのは、あなたが山岳圏、地域協創の現場に踏み出す気持ちをもつことです。
山岳圏森林・環境共生学コース、地域協創特別コースで、一緒に新しい時代をつくりましょう!!
森林政策学研究室の紹介
 森林政策学研究室では、人間と森林との関わりに注目して研究しています。
森林政策学研究室では、人間と森林との関わりに注目して研究しています。人間と森林との関わりは、木材などの生産はもちろん、日々の暮らしやレクレーションのための利用、二酸化炭素吸収や生物多様性の保全、災害の防止など、様々なものがあります。それらが現在うまくいっていないとしたら、それはなぜでしょうか。どのようにすればよくなるでしょうか。
森林政策学研究室が扱うのは、そうした社会的問題です。問題の中身を調べ、提案をし、最終的には社会をよりよくしていくことを目指しています。
森林政策学研究室で学ぶのは、(学界の名称でいえば)林業経済学という分野です。人間は、太古から森林を利用してきました。ときには収奪という形をとることもありました。こうした人間と森林との関わりは、資本主義社会のもとでは独特の形をとっています。森林を利用する動機が、個人や支配者のニーズから、利益の追求へと変わってくるためです。この資本主義社会という時代(人新世)の、人間と森林との関わりの歴史的な特殊性と、それによって生じている問題の解決方法を探るのが、林業経済学です。
「森林政策」とは、国や都道府県・市町村がおこなうものだけではありません。人々が「森林をこのようにしたい」と思い、誰かと協力して実行しようとすることそのものです。民主主義(デモクラシー)とは、民衆(デモス)自身が力(クラトス)をもっていることです。あなた自身が、森林政策の担い手なのです。
オープンキャンパス用の解説はこちら(2024年)
学部2~3年生むけ解説はこちら
研究室のようす
研究室日誌(随時更新)
 専攻研究(卒業論文にむけた研究)ではもちろん、それ以外の機会にも森林・林業に関係する現場の見学をしています。
専攻研究(卒業論文にむけた研究)ではもちろん、それ以外の機会にも森林・林業に関係する現場の見学をしています。
 地域で農林関連事業をおこなう人たちから、事業の課題をうかがい、学生がその解決のヒントとなりそうな研究を調べて考察し、報告して、それへの意見をいただくというゼミをしました。大学の隣にある伊那市産学官連携拠点施設 inadani seesの協力を得て実施しています(2023年度)。また、地域の森林の新しい利用方法について考え、村長・村議会に提案しました(2024年度)。
地域で農林関連事業をおこなう人たちから、事業の課題をうかがい、学生がその解決のヒントとなりそうな研究を調べて考察し、報告して、それへの意見をいただくというゼミをしました。大学の隣にある伊那市産学官連携拠点施設 inadani seesの協力を得て実施しています(2023年度)。また、地域の森林の新しい利用方法について考え、村長・村議会に提案しました(2024年度)。
 研究を通じて交流した地域での活動にもボランティアとして参加し、そこから農山村の現状を学んでいます。写真は、クマの出没対策として地域でおこなわれている、やぶの刈り払いに参加しているところ(2024年度)。
研究を通じて交流した地域での活動にもボランティアとして参加し、そこから農山村の現状を学んでいます。写真は、クマの出没対策として地域でおこなわれている、やぶの刈り払いに参加しているところ(2024年度)。
 山岳圏森林・環境共生学コース、地域協創特別コースに関係がある新聞記事を切り抜き、寸評を加えています。共通の話題をつくり、コースが学びの共同体になるようにしています。
山岳圏森林・環境共生学コース、地域協創特別コースに関係がある新聞記事を切り抜き、寸評を加えています。共通の話題をつくり、コースが学びの共同体になるようにしています。
2025年度は、研究室ではこんなことをする計画です。
 専攻研究(卒業論文にむけた研究)ではもちろん、それ以外の機会にも森林・林業に関係する現場の見学をしています。
専攻研究(卒業論文にむけた研究)ではもちろん、それ以外の機会にも森林・林業に関係する現場の見学をしています。 地域で農林関連事業をおこなう人たちから、事業の課題をうかがい、学生がその解決のヒントとなりそうな研究を調べて考察し、報告して、それへの意見をいただくというゼミをしました。大学の隣にある伊那市産学官連携拠点施設 inadani seesの協力を得て実施しています(2023年度)。また、地域の森林の新しい利用方法について考え、村長・村議会に提案しました(2024年度)。
地域で農林関連事業をおこなう人たちから、事業の課題をうかがい、学生がその解決のヒントとなりそうな研究を調べて考察し、報告して、それへの意見をいただくというゼミをしました。大学の隣にある伊那市産学官連携拠点施設 inadani seesの協力を得て実施しています(2023年度)。また、地域の森林の新しい利用方法について考え、村長・村議会に提案しました(2024年度)。 研究を通じて交流した地域での活動にもボランティアとして参加し、そこから農山村の現状を学んでいます。写真は、クマの出没対策として地域でおこなわれている、やぶの刈り払いに参加しているところ(2024年度)。
研究を通じて交流した地域での活動にもボランティアとして参加し、そこから農山村の現状を学んでいます。写真は、クマの出没対策として地域でおこなわれている、やぶの刈り払いに参加しているところ(2024年度)。 山岳圏森林・環境共生学コース、地域協創特別コースに関係がある新聞記事を切り抜き、寸評を加えています。共通の話題をつくり、コースが学びの共同体になるようにしています。
山岳圏森林・環境共生学コース、地域協創特別コースに関係がある新聞記事を切り抜き、寸評を加えています。共通の話題をつくり、コースが学びの共同体になるようにしています。2025年度は、研究室ではこんなことをする計画です。
- 地域活動をする ……各人が、なんらかの地域活動に参加して、地域の課題を伝聞や空想ではなく、実際に見聞きし体験します(森林以外の活動も含む)。
- 本を読む ……森林政策学・林業経済学を知るために読むべき本のリストを作成し、それを各人が読んでいきます。
- 月刊紙をつくる ……研究室で、毎月 読みものとなる雑紙(新聞)を発行します。その記事を書き、編集作業をおこないます。
学生の研究
 【2024年度】
【2024年度】- 「森林管理への市民参加」像を、海・川の管理論と比較する ……森林管理論で扱われてきた「市民参加」は、政策や計画の策定への参加(市民の意見を反映させること)だけに注目しがちだったのではないかと指摘しました。
- 「オープンな森林」の利用・管理 ……誰でも入れる森林が、過剰利用で めちゃくちゃになってしまわない ためには何が必要なのか、実例から明らかにしました。
- 地域に許容される里山利用とは何か ……地域の魅力向上のために里山利用をすすめるとき、どんな利用目的なら可能なのかを調べました。
- よく活用される学校林が形成された経緯 ……校舎に隣接した森林を、生徒だけでなく地域の人々も盛んに活用している小学校で、どのような工夫があったのかを調べました。
- 林業労働者の賃金の作業種・資格・地域間の差異 ……ハローワークの求人情報に示される林業労働者が雇用されるときの条件は、地域によって様々であることを明らかにしました。
- 中国の生態保全地域の山村経済 ……観賞用樹木の栽培をおこなっている山村を事例にとり、自然保護のための開発規制との両立について考察しました。
- 林業事業体による高性能林業機械の自社修理の最適範囲 ……林業現場に普及している高性能林業機械を、林業事業体は自らどのくらい修理できるのか、どのくらいまで修理するのが最適なのかを、事業体の規模ごとに明らかにしました(まったく修理しないと修理コストが上昇するが、修理するための技術や道具を備えるのもコストが上昇するため)。
- 「信州やまほいく」認定園の地域の自然活用を可能にする要素 ……長野県内の「信州やまほいく」認定園(幼稚園・保育園など)が、地域のどのような自然を活用しているのか、また森林などを活用する場合にはどのような調整が必要になっているかなどを調査しました。
- 「少年自然の家」等の教育施設による森林利活用の実態と人材 ……隣接する森林を利用した教育活動をおこなっている「少年自然の家」などの教育施設は、その人材をどう確保しているのかを調査しました。
- スキー場の跡地利用 ……スキー場(多くは森林からの転用)が廃止された跡地の利用方法と課題を調査しました。
- 林業労働災害統計で不可視化される事故の件数と性質 ……新聞報道のデータを用いて、労働災害の統計に含まれない災害がどのくらいあり、それはどのようなケースなのかを明らかにしました。
- 市街地における樹木保護制度の制度運用の実態 ……樹木保護制度が、実際に市街地でどのように運用されているのかを調査し、制度の問題点を考察しました。
- 「森林サービス産業」展開への自治体支援の比較 ……自治体は森林や森林保養施設を有していますが、これらといわゆる「森林サービス産業」との関連性について調査しました。
- 自然保育を通じた保育園維持・移住進展の要因 ……自然保育の推進によって人口減少にともなう休園を免れた事例を調査し、それが可能になった経緯や地域内の協力について明らかにしました。
- 自治体と市民組織とによる森林活用 ……地域の森林に一般市民を呼び込んでいく活動をしている団体の、団体立ち上げからの変化を調査しました。
卒業生の進路(過去5年間)

- 大学院進学(他大学)
- 都道府県庁
- 林業・木材産業
- 森林レクレーション産業・森林サービス産業
- その他産業
読みものなど
- 市町村の森林の可能性(『地方自治みえ』389号、2024年11月)
- 伊那市の自然環境から活用すべきものとは(2016年)
- 大学で役立つ、いくつかのテクニック(2021年)
- 調査・研究に使うリンク集
- 林業経済学・森林政策学に関する簡単な本(リスト)
- 森林・環境共生学に関連しそうな本を読んで適当に紹介するコーナー (2020~22年)
教員 三木敦朗(みき あつろう):助教
 メール:mikia26【あっと】shinshu-u.ac.jp
メール:mikia26【あっと】shinshu-u.ac.jp略歴:1978年滋賀県生まれ。信州大学学術研究院農学系 助教。博士(農学)。信州大学農学部森林科学科、同大学院農学研究科、岐阜大学大学院連合農学研究科を卒業後、(財)政治経済研究所、岩手大学を経て現職。
研究内容の詳細 Instagram
【 一般むけに書いたもの 】
多くの人に読んでもらうことを目的に書いたものです。
- 市町村の森林の可能性(『地方自治みえ』389号、2024年11月)
【 社会的な関わり 】
下記のような業務をさせたい場合は ご一報ください。森林政策・林業経済分野に関係のある内容でしたら、基本的にお引き受けします。まずは上記「一般むけに書いたもの」をご覧いただけると、どのような考えをしているかが分かると思います。委嘱手続きについては、こちらの様式を参照してください。
 南箕輪村消防団(第4分団第2部)団員(2021年度~。2025年度は機関班長) ……消防団に入りましょう! 地域に知り合いをつくるなら消防団です。
南箕輪村消防団(第4分団第2部)団員(2021年度~。2025年度は機関班長) ……消防団に入りましょう! 地域に知り合いをつくるなら消防団です。- 南箕輪村「大芝高原森林づくり協議会」委員(2023~2025年)
- 南箕輪村「南箕輪村地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定に関する特別委員会」委員長(2023年度)
- 伊那市「伊那市50年の森林(もり)ビジョン推進委員会」オブザーバー(2024~2025年度)
- 伊那市「50年の森林ビジョン Ina Valley Forest College 協議会」委員(2020~2024年度) ……「森に関わる100の仕事をつくる」を合い言葉にした「伊那谷フォレストカレッジ」の実施に関わっています。
- 伊那市「伊那市ミドリナ委員会」委員(2019年度~) ……市民と森林との距離を近くするための事業に関わっています。
- 箕輪町「箕輪町森林ビジョン検討委員会」委員長(2023年度)
- 辰野町「未来につなぐ辰野町の森ビジョン策定委員会」アドバイザー(2022~2023年度)、「未来につなぐ辰野町の森ビジョン推進委員会」アドバイザー(2025~26年度)
- 松本市「松本市森林再生市民会議 運営委員会」委員長(2022~2024年度)
- 佐久穂町「佐久穂町林業創生戦略研究会」委員(2025~2026年)
- 佐久穂町「さくほリビングカレッジ」聞き手(2022年度) ……youtubeで公開されています。森について(前編・後編)、狩猟について(前編・後編)、川について(前編・後編)、座談会(前編・後編)
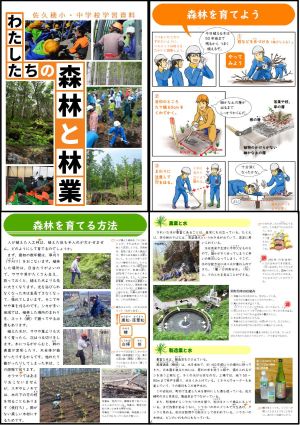 佐久穂町 小・中学校学習資料『わたしたちの森林と林業』作成(2017年度) ……小・中学校のキャリア教育(森林林業体験学習)の学習資料を作成しました(右図)。
佐久穂町 小・中学校学習資料『わたしたちの森林と林業』作成(2017年度) ……小・中学校のキャリア教育(森林林業体験学習)の学習資料を作成しました(右図)。- 長野県「みんなで支える森林づくり県民会議」構成員(2024年度~) ……長野県の森林づくり県民税の使い方についてチェックしています。
- 長野県上伊那地域振興局「みんなで支える森林づくり上伊那地域会議」座長(2020年度~)
- 長野県「長野県林業労働力確保促進基本計画検討会」座長(2021~2022年度)
- 長野県林業大学校 講師(「林政学」担当。2010年度~)
- 長野県林業大学校運営協議会 委員(2022年度~)
- 松本大学 非常勤講師(「自然と産業」「環境問題と循環型社会」担当。2025年度)
- 山梨県林業の担い手育成のあり方検討委員会 委員(2020年度)
- 日本林業経営者協会青年部 政策提言ワーキンググループ「新時代の森林管理・林業経営に向けた提言」のアドバイザー(2020年)
- 林野庁「森林・山村多面的機能発揮対策交付金評価検証検討委員会」委員(2020年度~)
- 林野庁(中部森林管理局)「国有林の地域別の森林計画等検討会」委員(2022年度~)
【 主な著作 】
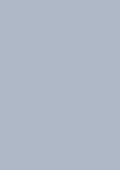 『森林と時間:森をめぐる地域の社会史』
『森林と時間:森をめぐる地域の社会史』山本伸幸編、新泉社、2024年
第1章「山造りに出会った人びと――島﨑洋路と森林塾」を執筆。
 『森林を育てる理由、伐る理由』
『森林を育てる理由、伐る理由』東京林業研究会編、咏林堂、2024年
「総理のためのスギ増伐」を執筆。
 『主伐期における林業機械化の課題とこれからの森づくり』
『主伐期における林業機械化の課題とこれからの森づくり』東京林業研究会編、咏林堂、2023年
「関わる人を増やす林業技術」「対談 AIと林業経済学分野の教育」を執筆・担当。
 『地域森林管理の長期持続性:欧州・日本の100年から読み解く未来』
『地域森林管理の長期持続性:欧州・日本の100年から読み解く未来』志賀和人・山本伸幸・早舩真智・平野悠一郎編、日本林業調査会、2023年
第2章8節「古絵図管理にみる地域意識:諏訪・上伊那の財産区・生産森林組合」を執筆。
 『テーマで探究 世界の食・農林漁業・環境 (3) ほんとうのエコシステムってなに?』
『テーマで探究 世界の食・農林漁業・環境 (3) ほんとうのエコシステムってなに?』二平章・佐藤宣子編、農山漁村文化協会、2023年
「林業の歴史」項を執筆。
 『東アジアのグローバル地域経済学:日韓台中の農村と都市』
『東アジアのグローバル地域経済学:日韓台中の農村と都市』加藤光一・大泉英次編、大月書店、2022年
第9章「テレワーク化・気候危機と森林共生社会」を執筆。
 『時代はさらに資本論:資本主義の終わりのはじまり』
『時代はさらに資本論:資本主義の終わりのはじまり』基礎経済科学研究所編、昭和堂、2021年
第11章「資本に呑み込まれる農業:地代論の可能性」を執筆(加藤光一と共著)。
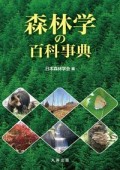 『森林学の百科事典』
『森林学の百科事典』日本森林学会編、丸善、2021年
「政策と法制度」項を執筆。
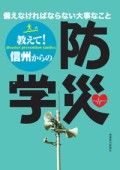 『教えて!信州からの防災学』
『教えて!信州からの防災学』信州大学地域防災減災センター、信濃毎日新聞社、2020年
「調理や暖房確保 非常時に有効まきストック」項を執筆。
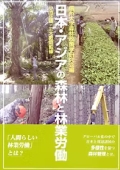 『日本・アジアの森林と林業労働』
『日本・アジアの森林と林業労働』信州大学林政策学研究会編、川辺書林、2013年
監修。「「やま」の兼業的・自給的利用」を執筆。
【 研究中の主なテーマ 】
- 林業労働問題 ……林業従事者が、より安全な労働環境で、仕事を継続できるようになるには、どうしたらいいか。
- 住民のための森林政策 ……森林の利用に関心をもつ地域住民が、利用できるようになるための制度・政策とはなにか。また、森林所有は今後どうあるべきか。
- ポスト現代社会と森林 ……森林は、日本経済の中でどのような役割を担ってきたのか、これからどうなるのか。
〒399-4598 長野県上伊那郡南箕輪村8304信州大学農学部森林政策学研究室
(研究室はB棟2階にあります)
© 信州大学農学部 森林政策学研究室
(研究室はB棟2階にあります)
© 信州大学農学部 森林政策学研究室